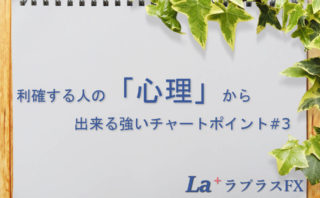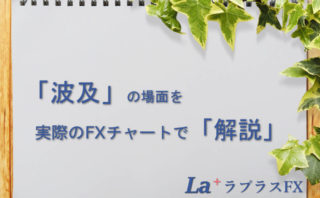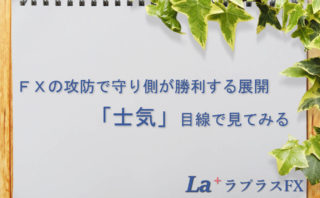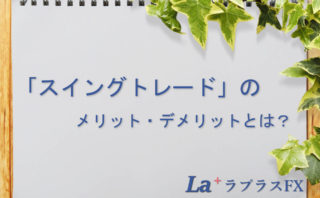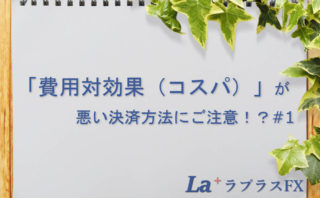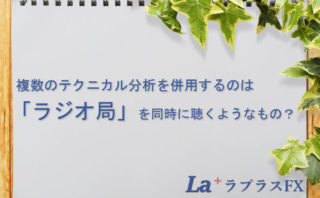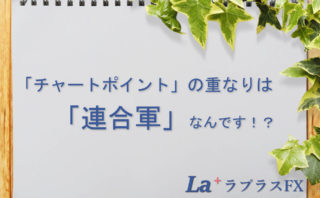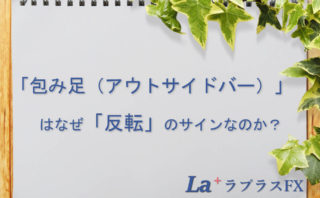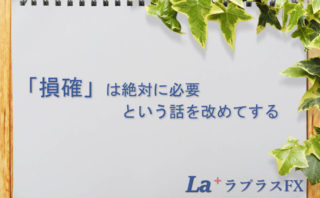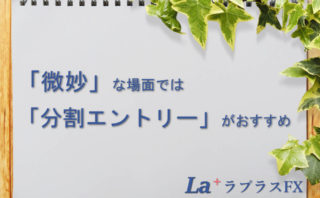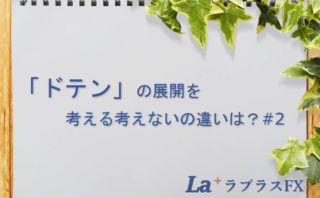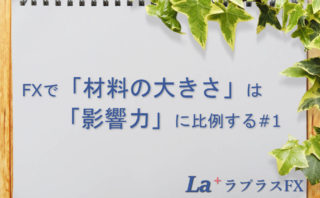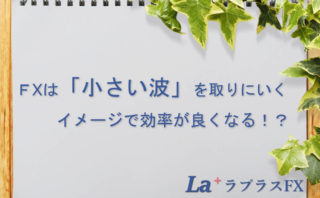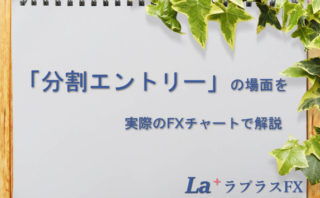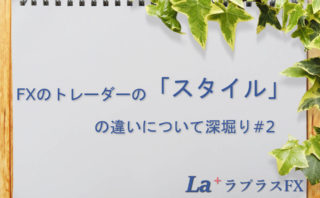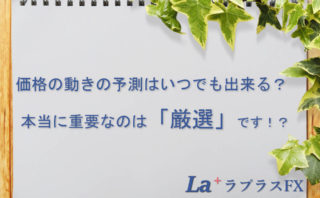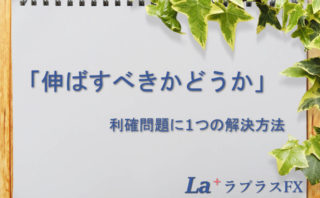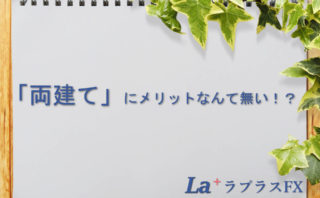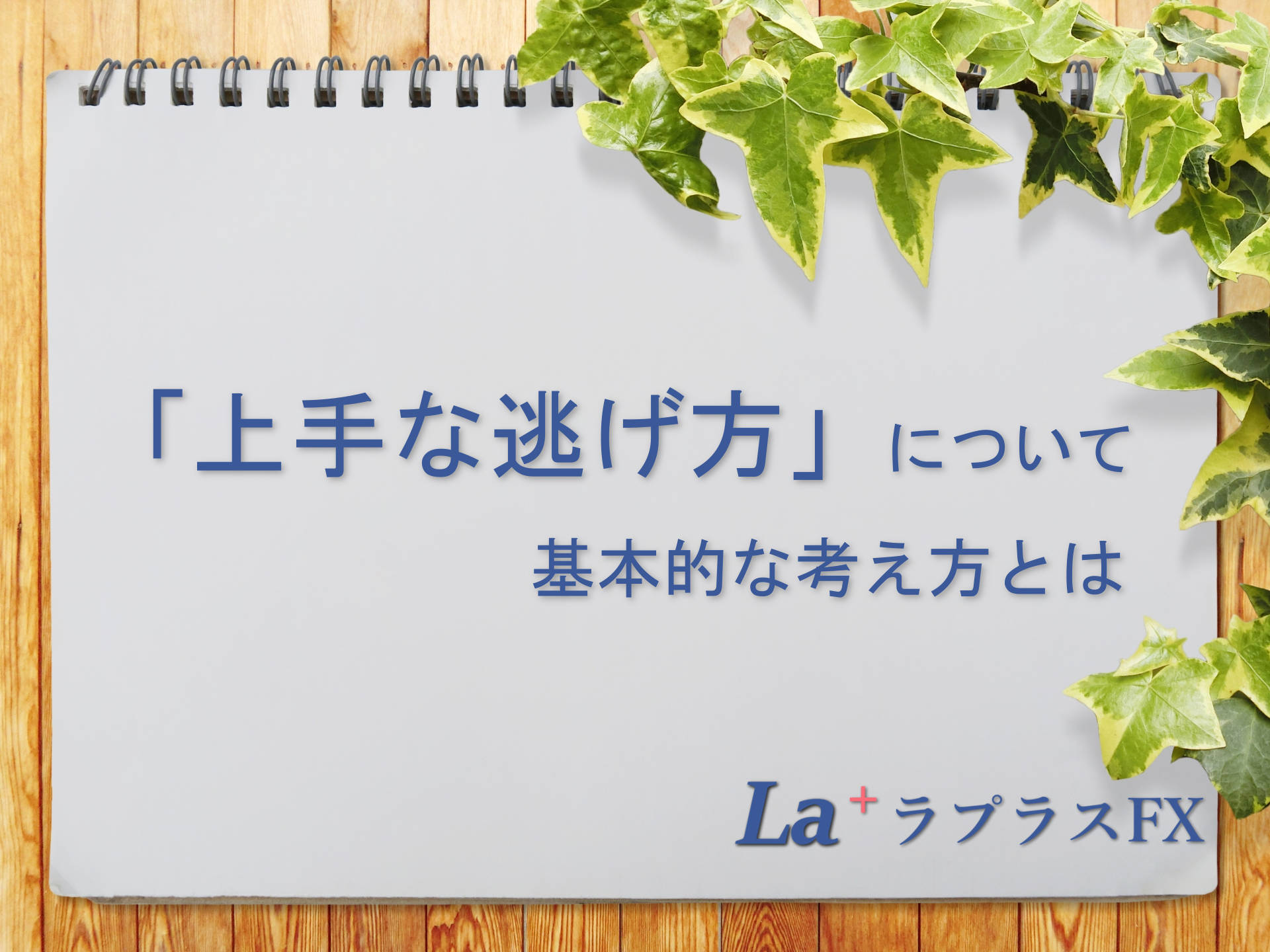FXの「逃げ方」
今回は、以前書いた「FXは逃げ方も重要」という記事の続きのような内容です。

FXに絶対はありません。
テクニカル分析で「優勢」な方を見極めてエントリーしたつもりでも、実際は違っていることは日常茶飯事です。
もちろん、その時は基本的には負けを受け入れて、しっかり損確をすれば良いのですが、場合によっては「逃げ方」次第で傷を浅くできることもあるんですね。
今回は、実際のFXチャートで上手な逃げ方の考え方について見ていきます。
まずは、下の画像を見てください。
M5レベルの上昇トレンドに対して押し目買いエントリーをした場面ですね。
損確の初期設定は上昇トレンドがダウ理論ベースで否定されてしまう、ダウ安値に入っている状態です。
戻りが浅いところからの買いエントリーですが、今回は「逃げ方」についてフォーカスしていますので、ラプラスFX的にこのトレードプランがどうなのかというのは置いておきます。
買いエントリーの後、上の画像のような展開になり、押し安値候補を下抜けてしまいました。
エントリー時にイメージしていた押し目買いは失敗ですね。
これは、「負の材料」です。
さて、この負の材料を持って、損確の位置を手前にずらして、早目に損確をすることで、損失額を小さくすることが出来ます。
しかし、これは上手い逃げ方でしょうか?
上の画像の展開で失敗したのは「浅いところからの押し目買い失敗」であって、上昇トレンドの継続自体が大きく否定されたわけではありませんね。
今回の買いエントリーはFIBO38.2%の浅いところからの早仕掛けだったので、ここからの押し目買いが伸びずに再調整の展開になっても、まだ深いところからの本命の押し目買いの期待が十分残っているんですね。
なので、押し安値候補を下抜けた時点で早目に損確するのを、「上手な逃げ方」とするのは少し違う気がしますね。
押し安値候補の下に損確を設定すること自体を否定するわけではありません。
もしも、買いエントリー後に上の画像のような展開で押し安値を下抜けた時点で決済をするような判断をするのであれば、エントリー時から損確の初期設定を押し安値候補に設定しておくべきですね。
早目の損確するのと何が違うのかというと、当たり前ですがトレードプランの損益率のバランスなどが変わってきます。
また、論理的にちぐはぐなトレードをしてしまっていることになるんですね。
買いエントリーをした時点で、上手くいかずに押し安値候補を下抜けてしまうケースは想定しているはずです。
その場合、「押し安値候補の下抜け=上昇トレンドの継続失敗」に即つながるイメージを持っていたのであれば、そもそもエントリー時から押し安値候補に損確を設定しておくべきなんですね。
もしくは、ダブルボトムの形なので押し安値候補を下抜けずに高値を抜けて伸びていく確率が高いとトレーダーが判断したのであれば、押し安値候補に損確を設定して勝負するのは自然ですね。
ですが、エントリー時に損確の初期設定をダウ安値に設定しているということは、このダウ安値を下抜けるまでは上昇トレンドが継続する可能性が高いというイメージを持っていて、そのイメージを根拠にトレードプランを建ててエントリーをしたはずなんですね。
なので、上の画像のような展開で早目に損確をするのは、少し違うのかなと。
もしも、押し安値候補を抜ける前に、横の展開を作ってから、下抜けてきたなどであれば、話は違ってきますね。
先ほどと違い、エントリー時には想定できなかったような展開になり、新たに考慮すべき重要なチャートポイントが出来上がった時などは、そこを使った決済というのは「上手な逃げ方」になりやすいですね。
初期設定した損確を手前にずらすという判断には、しっかりと論理的な根拠が欲しいということです。
エントリー後に、当初のイメージをくつがえすような大きな負の材料が発生した時に早目に決済をするというのが、上手な逃げ方になるわけです。
そもそも、当初からイメージされる範疇内の展開で損確するようであれば、初期設定の損確位置がおかしいという話です。
まとめ
FXの「上手な逃げ方」についての話でしたが、実際この話はとても難しい分野です。
FXのトレード技術の中で「決済」というのは、答えがあって答えがないような分野なんですよね。
「答えがある」というのは、実際のFXチャートの結果がすべてですから、「今回はここで決済しておけば良かった」という答えが明確に存在はしているわけです。
ですが、次もその形になったら、同じように決済すればよいかというとそういうわけでもないわけです。
今回は、あくまで上手な逃げ方の「考え方」についての話です。
この形になったら逃げた方が良いとか、この形であればまだ逃げなくて良いというのが、本旨ではないんですよね。
「形」なんてアナログ的なもので、毎回違う曖昧なものです。
なので、トレーダーが経験を持って「判断」をしないといけないんですね。
その時の考え方の基本の部分についての話でした。
基本的には「新しく発生した負の材料がトレードプランを覆す程に大きいものがどうかを判断する」ということです。
そして、この時にエントリー時点でも想定できるような展開であれば、それを許容する形で損確を設定しているはずだという点が注意点なわけですね。
ここに矛盾が発生してしまっているトレーダーは「恐怖心」に支配されてしまっている可能性があります。
リアルトレードには「恐怖心」が大なり小なり、人間である限りつきものなんですね。
買いエントリーした場合であれば、「陰線」が出現しただけで「このまま下落してしまうのでは?」という恐怖心が発生するわけです。
しかし、冷静になれば「価格というものは、そもそも上昇する場合でも上昇と下降を繰り返しながら伸びていくもの」であると分かるはずです。
トレーダーは恐怖心に支配されずに、常に論理的に判断しなくてはいけなんですね。
「恐怖心」の発生の仕方は人それぞれです。
小さな負の材料で急に怖くなって、あわてて決済してしまう人がいれば、大きな負の材料が発生しているにもかかわらず、損を確定することが怖くなって、決済できない人もいます。
「恐怖心」がトレードの判断に入ってきて良いことは1つもありません。
常に、淡々とチャート分析から導きだされる論理的な判断を持って行動しなくてはいけません。